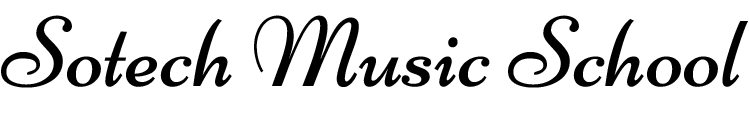1946年発表のこの作品、ポアロが登場する他の推理小説とは違って、主要な登場人物のキャラクターや心の動き、感情といったものがとてもきめ細かに描かれています。
まず冒頭に登場するルーシーですが、やかんはかけっぱなし、人の寝室に早朝から勝手に入ってくる、話は次々目まぐるしく変わっていくといった、人の気持ちやあとの事を全く考えていない等々、中頃では殺人事件を面白がっているようなセリフを平気で言ってたりして、この人は究極のお嬢様か、はたまたサイコパスかと思いました。(お嬢様は確かにそうですが)
次にヘンリエッタ。
真理を追求する芸術家であって、ポアロですら一目置く冷静さと判断力に富む女性。美貌の持ち主で男性にはモテまくり。「私はジョンの愛人だったわ」なんて自分から白状する正直な人。
そしてガーダですが、容姿は冴えず平凡で知性はなく、全てジョンの言いなりになっているダメ妻と周囲の者からはバカにされながらも、ジョンには深い愛情を持っています。
そして内心では自分はそんなにバカじゃないのよ、と思っていて意外に賢い女性。人を自分に都合よく使える人でもあります。
この話は全体的にオブラートに包まれているような、殺人事件は発生はしますが、血なまぐさくなく、舞台の一場面のような現実離れしたイメージがあります。
それというのも殺人のトリックとか証拠品といったものよりも人の心の情景を描くのに重点がおかれているのかと思います。
そういう意味ではこの物語にあえてポアロが出る必要なかったんじゃないかと私は思いますし、ポアロ自身も傍観者としての立ち位置に徹しています。
ついでにヴェロニカもいつの間にか話から消えてるので、ジョン殺害のきっかけを作っただけで、本筋から見たらいらない人かも。
この話で一番幸せになったのはミッジですね。エドワードがミッジを彼女が働く店から連れ出すシーンが一番印象に残りました。二人の考え方の相違が貴族と労働者階級との違いとなって表れています。
この話の主役としてヘンリエッタの心の描写が多く描かれています。が同時にガーダに対する作者の純粋な愛に添い遂げさせたいという深い優しい愛情が感じられます。
陽のヘンリエッタが明るく輝けば輝くほど、陰としてのガーダの存在がはっきり浮かび上がってくるような二人の関係。
この話は「春にして君を離れ」を思わせる心理描写が長く、読むあいだ中、うっ屈とした気持ちが常にあって、その気持ちから逃れたくてほぼ一気読みした一冊です。
今回は少し影が薄かったポアロですが、名セリフがいくつかあります。
さすがポアロ
ポアロ名セリフ
「ほんとの手がかりは関係者の人間関係の中にあるものですよ」
ポアロがヘンリエッタに言った言葉
「人間の真の悲劇は求めるものを手に入れることである」
これはまさしくジョンに当てはまります
総論
灰色の脳細胞より嗅覚
(さなぎ感想)
登場人物
ヘンリー.アンカテル卿 行政官
ルーシー ジョフリーおじさまの一人娘
ミッジ.ハードカースル
ヘンリエッタ.サヴァナク 彫刻家
ジョン.クリストウ 医者
その秘書 ベリル.コリンズ
ガーダ ジョンの妻
二人の息子 テレンス12才
娘 ジーナ9才
メイド ベリル、コリンズ
ディヴィッド.アンカテル
エドワード.アンカテル(エインズウィック相続人)ルーシーのいとこ
ガション 執事
シモンズ メイド
ヴェロニカ.クレイ 映画女優
エルシー.バターソン ガーダの姉
イグドラシル 樫の木
四阿 あずまや
2022.1.25記