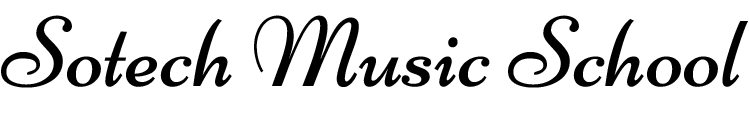この作品は1957年に発表されたノンシリーズの1つで、アガサクリスティが自身のベスト10にも選ばれています。
ただ、あとがきの解説者はこれは失敗作だと言っています。
なぜか❔
あとがきを読んで私もなるほどと思いましたが、ポアロやマープルといったメインの探偵役がこの作品にはありません。
ジャックの無罪を明らかにしたキュルガリが最初探偵役をつとめますが、彼はすぐ消え、メアリの夫フィリップが途中からしゃしゃり出て、ゲーム感覚で犯人像を割り出そうとします。それからキュルガリが終わり近くになって出現します。警察も再調査を始めるけど何を調べてるかまったくわからないです。そのためとってつけたように事件が解決してしまってます。
ヘスターとキュルガリのロマンスも物語を締めくくるにはちょっとお粗末なものでした。
犯人像にしても、家政婦が犯人というのはこの作品が私の知るかぎり初めての事で、いくら若い男にだまされたからといって、長年仕えてきた主人を殺すことができるんでしょうか?
まして自分の身が危なくなったからといって、自分を慕っているティナをナイフで刺すなんて、実直なカーステンのキャラクターからみて違和感ありすぎて納得できないのが本音です。
医者か誰かが語ったセリフに「殺人者には二種類ある。一つは人を殺すのが恐ろしくない人、もう一つは殺人という不幸を背負い続けて生きられない人。そういう人は自白するか、自分のせいじゃないと自己弁護するしかない」とありますが、(カーステンは後者の方だと思いますが)ジャックが刑務所に入って死んだ後もそのままアージル家で働いているのは信じられないです。
この作品は推理小説というよりは人間の内面を描くのに重点がおかれていると思います。
母親に捨てられたマイケルはレイチェルを恨んでいたが、実は実の母を恨んでいるのだと気付き、リオとグエンダは互いに相手を疑い、ヘスターは恋人のドナルドに自分が疑われてると知ってショックを受け、そしてメアリは夫フィリップを自分だけのものにしようと固執します。そういう個々の内にある疑惑、嫉妬、恨みといったものを自問自答している姿がありありと描かれています。
一度その深みにはまったら、もうその先はアリ地獄のように自らをとらえて放さない。ヘスターのセリフにある「問題は有罪じゃない、無罪なのです。」
その通り、まさに無罪の人間が各々疑心暗鬼にとらわれるさまが面白くてたまりませんでした。
冒頭の風景描写も暗い、冷たい静けさがまざまざと目に浮かび、これから始まる物語を予感させられました。
環境は人間の育成に大いに関係があるが、それが全てではない。その事をしみじみ考えさせられる哲学書にもなる、私にとってまた読みたいと思わせた貴重な一冊です。
「春にして君を離れ」と併せて読んでいただきたい、内面のドロトロをさらけ出した、アガサクリスティのとんでもない失敗作かつ最高の作品です。
アイロニー
皮肉 西洋では自分の意図する意味と反対の意味を持つ表現によって意図する意味を表す修辞技法をさす
登場人物
アーサー.キュルガリ 地理学者
レイチェル.アージル(旧姓コンスタム)大富豪ルドルフ.コンスタムの一人娘
リオ レイチェルの夫
レイチェルの養子たち
ヘスター
マイケル(ミッキー)
ジャック(ジャッコ) 元妻モーリンは再婚夫ジョー.クレッグ
メアリ(ポリー).デュラント 夫フィリップ(脊椎カリエス)
ティナ(クリスィナ)
彼女たちの住まいサニー.ポイトン(昔の呼び名まむしの出鼻)
アンドリュー.マーシャル 弁護士
グエンダ.ヴオーン リオの秘書
カーステン.リンツトロム アージル家家政婦
ドナルド(ドン)クレイグ 若い医師、ヘスターと恋仲
マクマスター 老医師
フィニー 警察本部長
ヒュイッシ 警視
シリル.グリーン 坊や
2022.2.27記